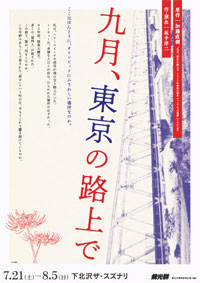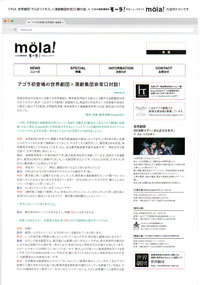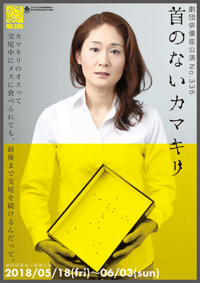認定特定非営利活動法人STスポット横浜が、9月1日に「【調査】文化芸術の中間支援組織の現状について」を発表しました。
舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)の政策提言調査室が、会員以外も参加出来る勉強会「文化芸術における法律」を開催します。
燐光群全作品でベスト3に入るのではないかと思われる『九月、東京の路上で』(7/21~8/5、東京・ザ・スズナリ)。本番では上演されなかった、前説を兼ねた冒頭シーンの台本が、坂手洋二氏のブログで8月11日公開されました。
マスコミには毎日膨大な企画書や招待状が届きます。開封するだけで一苦労なので、個人宛でない場合は、アルバイトが開封して箱に入れておくだけのところも多いのではないかと想像します。個人宛であっても、無名の団体からの企画書は目も通されないのではないかと思います。それだけ量が多いので、よほど興味を持たれる工夫が必要です。
オープンから1年経った「札幌観劇人の語り場」。ここで異彩を放つのが、「マサコさんの部屋」という企画コーナーです。
この10年で、ビジネス社会に最も浸透した舞台用語はなんでしょう。社会人の方なら実感されるはずですが、それは「座組」だと思います。いまはビジネスの現場で、誰でも普通に使うと思います。10年前は意味自体が通じないことが多かったようです。
こまばアゴラ劇場(東京・駒場)に今秋登場する愛媛・鹿児島の2カンパニーが、九州の演劇ニュースサイト「möla!」で対談を行ない、その前半をチラシとして折り込んでいます。
まだチラシの現物は入手していませんが、横山拓也氏(iaku)が劇団俳優座に書き下ろす『首のないカマキリ』(5/18~6/3、東京・俳優座稽古場)の宣伝美術が、デザイナーは異なるのに、iakuのチラシテイストを踏襲しています。めずらしい事例なので記しておきます。
劇団6番シード(本拠地・東京都豊島区)の票券管理団体である合同会社劇団6番シード群馬事務所(群馬県太田市)が、4月24日~29日にフリースペース「犀の穴」(東京・十条)で開催する「舞台制作講座」が来週に迫りました。公演に付随したインターンシップではなく、講座のためだけに劇場を使うのは非常にめずらしく、記録に残す価値があると考えます。